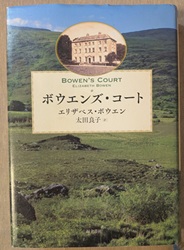| 初出 「図書新聞」3709号 2025年 11月1日 |
書評・評論 |
Home ホーム 更新・短信 The Latest Notes 新作エッセイ Essays since 2018 |
書評・評論 (太田良子 訳) 2025年7月30日発行 A5版416頁 本体3500円 而立書房 北田敬子 アングロ・アイリッシュの作家、エリザベス・ボウエン1899-1963)が1937年に執筆を開始し、1941年に執筆を終了した後、時を経て1964年に改訂版を上梓した作品が、2025年7月に日本語訳で出版された。この間に生起したアイルランドの、そして日本を含む世界の様々な事象は実に多岐にわたる。混沌と狂乱と言っても過言ではない近・現代史の中で、アイルランドのコーク州にボウエンズ・コートという屋敷は粛然と建ちあがり、そして消えて行った。一つの場所の一つの建物と、それをめぐる一族の興亡を作家は、ノンフィクションとして描く。アングロ・アイリッシュという立場が、アイルランドでどのような意味を持つものであったかについても詳らかにされる。 エリザベス・ボウエンは短編集を中心とする数多くの小説作品によって二十世紀の英文学にその名を刻む。日本語に翻訳された作品も多く、とりわけ本作の訳者である太田良子の訳業は枚挙にいとまがない。ミステリアスで緊張感漲る希代のストーリーテラーによる、この一見取りつきにくいファミリー・ヒストリーが今なぜこの時期に出版されたのか問いかけながら評者はページをめくった。 土地や人物の関係を読み解くのは難題である。だが本書の見開きに掲げられた、ボウエンズ・コートを中心とするマロウ、ファーモイ、ミッチェルズタウン、チャールヴィル、キルボーレンなどの街や、オーベグ川、ブラックウオーター川などの河川が収まる一帯の地図、そしてヘンリー一世に始まり、ヘンリー六世とその一人娘エリザベス・ボウエンに連なる「ボウエン一族の家系図」が、必携ガイドであることが明らかになってくると解読の手掛かりが得られる。 ある意味ではとても狭い世界のことを丹念に記録する歴史書ではある。長子相続を旨とする遺産をめぐる確執は、どこにでもある騒動かもしれない。ウエールズ出身のヘンリー一世が、オリヴァー・クロムエルのアイルランド侵攻に従って十七世紀中葉に海峡を渡って以来、一族はアイルランドのコーク界隈に所領を得て、ほぼ一貫して在郷地主としてその場所に存在し続けた。 エリザベス・ボウエンは残された記録を丹念に読み解き、つなぎ合わせ、歴代の領主とその家族について事細かに記録する。(時折、その細かさに面食らっているだろう読者を気遣う文言の差し挟まれることもある。)似たような名前が繰り返されるとき、「家系図」が読書中の遭難を回避する唯一の手掛かりになると言ったら語弊があるだろうか? ヘンリー一世(1659年没)から、ジョン一世(1718年没)、ジョン二世(1720年没)、ヘンリー二世(1722年没) と下り、ヘンリー三世(1723年-1788年)がボウエンズ・コートの建立を決意した。完成まで十年を経て一家が入居を果たしたのは1776年のことである。そもそも屋敷のあったマロウは1750年代に絶頂期を迎えていた。ひと頃はアイルランドの「バース」と呼ばれたほど保養地としての魅力があったものの、その後は衰退し変哲のない田舎町となった。一族はこの屋敷でアイリッシュ・カントリー・ジェントリーの暮らしを営んできた。さらにヘンリー四世(1762年-1837年)をはさんでロバート(1769年-1827年)と続き、ヘンリー五世(1808年-1841年)がここに入居したのは1817年。さらにまた別のロバート(1830年-1888年)と呼ばれるその次の当主がエリザベス・ボウエンの祖父に当たる。 曾祖父、祖父、父ヘンリー六世(1862年-1930年)の行状を記録と記憶の両面から辿る作者は、屋敷の中で繰り広げられる家族の歴史のみならず、1847年から1849年にかけて最大の危機を迎えたジャガイモの大飢饉のときの様子(ボウエンズ・コートでは飢えた人々にスープを振舞ったものの、所管の教会墓地には棺桶なしで埋められた餓死者の遺体が山をなしていた)、徐々に激しさを増していくイングランドとアイルランドの独立をめぐる攻防、とりわけアイリッシュからの圧力を書き込まずにいられなくなっていく。実際にボウエンズ・コートにも近隣の邸宅同様襲撃・焼き討ちの危機は何度もあった。 オックスフォードで学び法廷弁護士のキャリアを築いた父がパーネルの同時代人であったにもかかわらず、政治には一切関わらなかったこと、両親はアイルランド文芸復興やそれに連なる詩人・劇作家・小説家たち、ゲール語の復活にも興味を示さずに過ごしていたことをエリザベスは淡々とした筆致で書いている。一族のアイリッシュネスへの共感の欠如とうねる時代の変化にさほど敏感でなかったことは否定できない。 この作品の中で度々言及される「プロテスタント・アングリカンのアセンダンシー(支配制度)」に注目するなら、元々住んでいたカトリック教徒から土地を奪った侵略者であるイングランド人(たとえ出自がウェールズであろうとも)の立場が揺らいでいたことは明白である。ボウエン家の人々は暴利をむさぼる悪地主ではなかったとしても、農場の管理・収穫からの取り立てを厳守する限り永遠にアイリッシュと同化することはあり得ない。征服者はアイルランドの土地では異分子であり続ける。そして、独立を果たしたアイルランド、現代の資本主義世界の中で、旧来の地主としての「本業」を全うできなくなった一族の末裔がボウエンズ・コートを手放さざるを得なかった必然が見えてくる。 最後の相続人エリザベス・ボウエンが屋敷の物理的終焉を含めてボウエンズ・コートの命運を執筆したことで、アングロ・アイリッシュのアイルランドにおける実相が記された。そこには幽霊も出ない。妖精も住んでいない。そこは血みどろの戦場にもなった。侵略者は植民地とどう関わったのか。偏りはあろう。しかし『ボウエンズ・コート』は紛れもなくアイルランドという場所と人間たちへの哀惜の念が、深く、重く、丹精込めて描かれた作品であることは間違いない。あらためてボウエンの創作に立ち返るとき、作家のバックボーンがどこにあるか明かす必読の書となることだろう。
【註】 |
| 初出 「図書新聞」3709号 2025年 11月1日 |
Home ホーム 更新・短信 The Latest Notes 新作エッセイ Essays since 2018 |